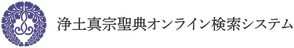〔概說〕
本鈔の著者である聖覚法印は、天台唱導(說敎)の祖として名声を博した藤原澄憲を父にもち、比叡山に上り修學をなして澄憲の安居院を継いだことから安居院法印聖覚と呼ばれた。澄憲と同様に唱導にすぐれ安居院流の唱導師として名高い。法印と源空(法然)聖人との関係については、『明義進行集』に「聖人つねにのたまひけるは吾が後に念佛往生の義すぐにいはむずる人は聖覺と隆寛となりと云々」とあるように、念仏往生の法義を正しく受け継いだ者として、隆寛律師とともにその名が挙げられている。このように、法印は源空聖人から絶大なる信賴を得ていたことが窺え、本鈔を著して念仏往生の正義を明らかにされ、専修念仏の思想の弘通に努められている。ただし、『金綱集』によると、法印は源空聖人が示寂されて十五年後に起きた嘉禄の法難(一二二七)に際して、専修念仏の弾圧要請をした一人として名を連ねており、この背景には、念仏敎団内部の対立抗争があったことが原因ではないかという指摘もある。
しかしながら宗祖は、源空聖人の念仏往生の正統なる伝承者として、法印と隆寛律師を法兄として敬慕されている。その様子は、宗祖が関東在住の頃から本鈔を敬重され幾度となく書写されたことや、それを門弟に与えて熟読するよう勸められたことが御消息などから知られる。宗祖は後に本鈔の題号や引証された経釈の要文を註釈した『唯信鈔文意』を著し、本鈔の法義を更に展開されている。
本鈔は、源空聖人より相承した念仏往生の要義を述べてただ信心を肝要とすることを明らかにされたものである。すなわち、前半では仏道に聖道門と浄土門の二門がある中、末世の衆生にかなうものは浄土門であるとし、その浄土門には、諸行によって往生を願う諸行往生と称名念仏によって往生を願う念仏往生とがあると說く。その中、他力の念仏往生こそが仏の本願にかなうものであり、自力の諸行では往生をとげがたい旨を述べる。更に念仏往生の中に専修と雑修とを示して、阿弥陀仏の本願を信じ、ただ念仏一行をつとめる三心具足の専修がすぐれることを明確にし、念仏には信心を要とすることが述べられる。また後半には(一)臨終と尋常の念仏、(二)弥陀願力と先世の罪業、(三)五逆と宿善、(四)一念と多念についての不審をあげてこれを決択される。なお「乃至十念と一念随喜」を加えて五種とする說もある。
本鈔の法印自筆本は現存しないが、承久三(一二二一)年八月に法印が本鈔を著されたことが宗祖の書写奥書よりわかっている。高田派専修寺蔵親鸞聖人真筆本(信証本)の奥書には、「草本云承久三歲仲秋中旬第四日安居院法印聖覺作寛喜二歲仲夏下旬第五日以彼草本眞筆愚禿釋親鸞書寫之」とあるように、宗祖が本鈔を最初に書写されたのは、本鈔が述作された九年後の寛喜二(一二三〇)年五月、宗祖五十八歲であり、関東在住の時に法印の自筆本から書写されている。宗祖は、以来本鈔を生涯に少なくとも八回書写されている。
本鈔は、高田派専修寺蔵親鸞聖人真筆本(信証本)を底本とし、本派本願寺蔵親鸞聖人真筆本(本願寺蔵本)、高田派専修寺蔵文曆二年親鸞聖人真筆本(平仮名本)、親鸞聖人真筆断簡(岐阜県照蓮寺、神奈川県上正寺、富山県善德寺、鹿児島県性応寺、福井県南光寺、茨城県願入寺、真宗大谷派)、真宗法要所収本を対校本とした。
信証本は、表紙中央に「唯信鈔」と外題がある。左下の袖書は、磨損と剝落により十分に判読し得ないが、同寺所蔵『唯信鈔文意』康元二年正月二十七日親鸞聖人真筆本の表紙袖書と同じ「釋覺然」であると考えられている。旧表紙は、本紙共紙で中央に「唯信鈔」との外題があり、左下に「釋信證」、右下に「釋覺然」と袖書が墨書される。この外題と「釋信證」は本文と同時にしたためられた筆と認められ、宗祖が自ら書写して信証に与えられたことを示している。これに対して「釋覺然」の袖書は異時筆であり、信証に与えた後、更に覚然の手に渡る際に書き加えたことが窺い知られる。本文には句点や圏發点が朱筆によって加えられている。奥書には寛喜二年の書写とあるが、筆風は明かに老年期の手になり、『唯信鈔文意』(正月二十七日本)と寸法や料紙、更に筆も一致することから、信証本は正月二十七日本と共に康元二年に書写せられたものと考えられている。従って寛喜二年は、宗祖書写の底本になった原本の奥書とみることができる。体裁は半葉五行、一行十六字内外である。
本願寺蔵本は、旧表紙中央に「唯信鈔」との外題があり、左下に「釋專□」と袖書がある。旧表紙見返には、同寺蔵『観無量寿経註』と同様の圏發点の図解を示す。「舌内字根脤内字貪」は別筆であり、当本のみに記される。本文は信証本と比較して若い筆風であり、宗祖の八十歲頃の筆と見られる。卷尾には「草本曰承久三歲仲秋中旬第四日安居院法印聖覺作」の根本奥書があり、本文と同筆であるが、それに続く「寛喜二歲仲夏下旬第五日以彼眞筆草本寫之也」の書写奥書は別筆である。体裁は半葉五行、一行十三字内外である。
平仮名本は、平仮名交じり文であったと考えられる法印自筆本や寛喜二年本を、そのまま写したものと推測されている。宗祖と門弟との間では、平仮名交じりのものを聖敎として取り扱う場合は、片仮名交じり文に書き改めるという慣行があったようで、これに従えば当本は門弟に書き与える前の手控え本とみることができる。当本は、当初八十葉ほどの袋綴であったと考えられており、現在は卷首から三分の一の部分が失われている。当本は宗祖六十三歲の筆跡であることが明確となっており、宗祖の筆跡の年代判定に重要な基準とされる。宗祖真筆のうち年代の明確なものは八十歲代に多く、六十歲代では当本が唯一である。奥書には、本文と同筆で「本云 承久三歲仲秋中旬第四日以安居院法印聖覺寛喜二歲仲夏下旬第五日以彼眞筆草本書寫之」竝びに「文曆二歲W乙未R六月十九日愚禿親鸞書之」との書写奥書がある。このうち「寛喜二歲…以彼」は、脫落を補った宗祖の追筆で時代は下ると考えられる。奥書の上欄に、本文と別筆で「御年五十五也」と「文曆二年W乙未R三月五日御入滅也」との書き入れがある。次いで「聖覺法印表白文」と但馬親王に宛てた「御念佛之間用意聖覺返事」とが書写されており、宗祖により同時に書写されている。体裁は半葉五行、一行十三字内外である。尙、平仮名本の本文紙背には、『見聞集』とよばれる経典等の抜粋が書写されてある(小部集Ⅰ『見聞集』解說参照)。
真宗法要は、本願寺蔵本と同系統で同じ奥書がある。最後に「愚禿釋親鸞」を加える。
底本・対校本
- ・ 高田派専修寺蔵親鸞聖人真筆本(信証本)
- ・ 本派本願寺蔵親鸞聖人真筆本
- ・ 高田派専修寺蔵文曆二年親鸞聖人真筆本(平仮名本)
- ・ 親鸞聖人真筆断簡